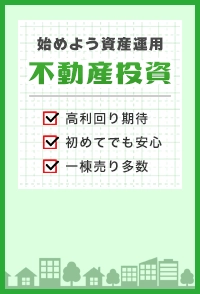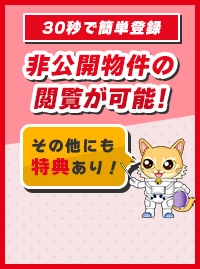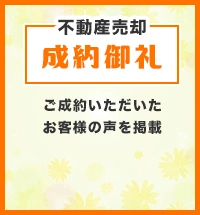平成バブルが残した“建築の爪痕”──現在は令和バブル?日本のバブル遺産を歩く|渋谷の仲介+α(プラスアルファ)|ロケット不動産株式会社
平成バブルが残した“建築の爪痕”──現在は令和バブル?日本のバブル遺産を歩く
こんにちは。ロケット不動産の渋谷です。
今日は少し、街と経済の“記憶”をたどってみたいと思います。
1980年代後半から1990年代初頭、日本はバブル経済の絶頂期にありました。
「土地は下がらない」「持つ者が勝つ」――そんな神話が信じられていた時代。
不動産価格は高騰を続け、銀行融資は容易に受けられ、全国で次々と“豪華絢爛な建物”が建てられました。
その一方で、バブル崩壊後に残されたのは、使われなくなった“ハコモノ”や、
廃墟のように朽ち果てたリゾート施設たち。
いま私たちは、それらを「バブル遺産」と呼んでいます。
第1章:土地神話が生んだ「ハコモノ建築」たち
1980年代の終盤、日本中の自治体が競うように公共施設を建設しました。
それが「ハコモノ」と呼ばれる大型の建築群です。
美術館、ホール、記念館、研究都市――。
バブル期には、地方財政が潤っていたこともあり、
“何に使うか”よりも“建てることそのもの”が目的になっていた節もあります。
代表的なバブル遺産をいくつか挙げると、
-
釧路市生涯学習センター(北海道)
-
吉備高原都市(岡山県)
-
世界平和大観音像(兵庫県)
-
アジア太平洋トレードセンター(大阪府)
-
横浜駅西口シンボルタワー(神奈川県)
-
新梅田シティ・梅田スカイビル(大阪府)
たとえば、横浜駅西口の楕円形のタワー「風の棟」は、
伊東豊雄氏設計の“換気塔”です。
ただの空調設備にここまでデザインを施す――
この発想こそ“バブルの象徴”と言えるでしょう。
また、新梅田シティは当初「時代遅れの遺産」と批判されましたが、
のちに外国人観光客に人気を集め、
「世界の名建築20」にも選出されるほどに再評価されました。
かつての“浪費”が、時を経て“文化”として残った例です。
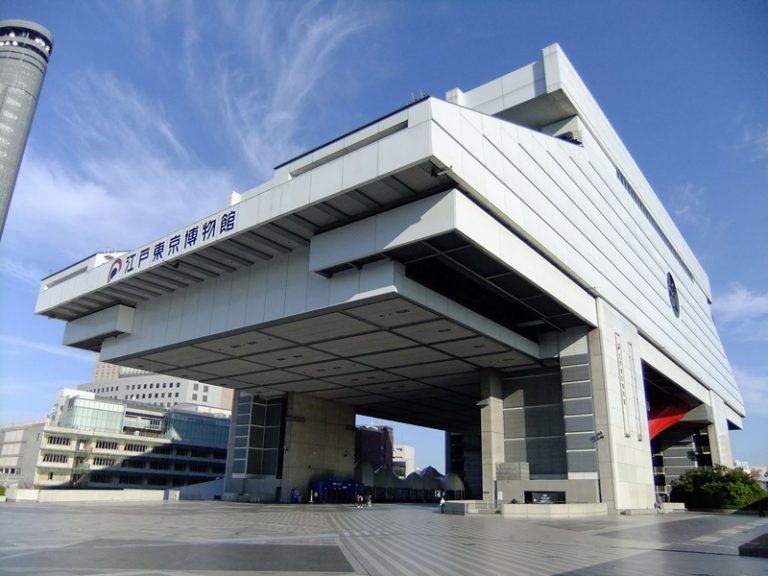
第2章:ホテル・リゾート・マンション編 ― 豪華さの極み
民間分野でも、バブルの熱狂は止まりませんでした。
特にホテルやリゾート開発では、“資産を誇る建築”が次々と誕生します。
代表例を挙げると、
-
ホテル川久(和歌山県)
-
ウェスティンホテル東京(東京都)
-
ホテル雅叙園東京(東京都)
-
ヴィクトリア・タワー湯沢(新潟県)
-
北の京・芦別(北海道)
-
シーガイアコンベンションセンター(宮崎県)
中でもホテル川久は、“金色の宮殿”と呼ばれた伝説的な建築。
大理石と金箔をふんだんに使い、ムラーノガラスを輸入、
総工費は約400億円――まさに「夢を建てた」時代の象徴です。
しかし、バブル崩壊後、こうしたリゾート施設の多くは経営難に陥り、
今では廃墟としてYouTuberや写真家が訪れる“負の遺産”にもなっています。
とはいえ、その建築的価値やデザインの美しさは、今も人を惹きつけます。
第3章:令和に蘇る“新しい豪華” ― 令和バブル?
そして今。
私たちは「もうバブルは終わった」と思いながら、
再び“静かな熱狂”の中にいるのかもしれません。
東京・麻布台に2023年誕生した Azabudai Hills(麻布台ヒルズ)。
総事業費は約6,400億円。
居住・商業・オフィス・文化・教育が融合した超複合都市です。
「街そのものがひとつの建築作品」という発想は、
まさに令和時代の“ラグジュアリーの再定義”でしょう。
また、同じく2023年に完成した Tokyu Kabukicho Tower は、
エンタメ・ホテル・劇場を融合した“夜のランドマーク”。
高層階に2つの高級ホテルを備え、下層部ではライブ、映画、イベントが行われる。
この「遊び・仕事・滞在・発信」の複合体こそ、
令和バブルの象徴的建築といえるかもしれません。
他にも、
-
虎ノ門ヒルズステーションタワー(2023年)
-
渋谷スクランブルスクエア(2019年)
-
晴海フラッグ(2024年入居開始)
-
東京ミッドタウン八重洲(2023年)
など、いずれも“機能性と象徴性”を兼ね備えた建築群が次々と登場。
派手な装飾ではなく、**「機能×ブランド×体験」**が豪華さを形作っています。
第4章:バブルの形は変わっても、「人の欲」は変わらない
平成のバブル建築が「形の豪華」なら、
令和のバブル建築は「データと体験の豪華」。
AI査定・SNS戦略・海外資金――
目には見えない価値が、街の価格を動かす時代です。
しかしその根底にあるのは、
「良い場所に住みたい」「人に誇れる建物を持ちたい」という、
いつの時代も変わらぬ“人の欲”です。
バブルは経済現象であると同時に、
人間の価値観の映し鏡でもあります。
だからこそ、平成の“過剰な美学”も、令和の“合理的な豪華さ”も、
どちらも私たちの文化として受け継ぐべきだと思います。
結び:街に夢を残すということ
バブルの教訓とは、
「無駄を恐れすぎるな」ということかもしれません。
平成の建築は確かに過剰でした。
しかし、あの時代には“夢を形にしよう”という情熱があった。
令和の時代に求められるのは、
その情熱を“理性と調和させる力”です。
豪華でも、堅実でも、街は人が作る。
そして、不動産とは“人の夢と経済の結晶”なのです。
次の時代の建築が、どんな爪痕を残すのか――
私たち不動産業者こそ、しっかり見届けていきたいと思います。
ページ作成日 2025-10-19
- 1月7日は「七草粥」──なぜ“七草”なのか
- 1300年続く神田明神の歴史と街
- 東京は、2人の武将の「土地を見る目」から始まった
- ありがとう、島内宏明選手 ―― ヘルメットが飛ぶフルスイングと、楽天一筋14年 ――
- 2026年最初のスーパームーン ―「夜の景色」が住まいの価値を映し出す日―
- 1月2日、東京初雪。明日の路面凍結にご注意を
- 初夢に見る「一富士二鷹三茄子」と、縁起のいい住まいの話
- 大晦日と年越しそば ― 江戸から続く“締めの一杯”と、住まいの話 ―
- 12月30日は地下鉄記念日 ―― 地下に刻まれた100年の歴史と、不動産価値の正体 ――
- SF映画の世界が現実に ― 2026年、家が“変形”する時代へ ―
- もっとみる