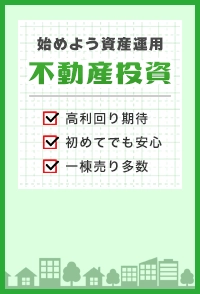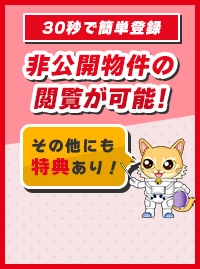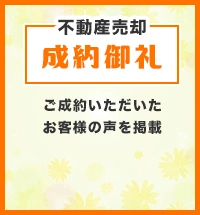こんにちは。ロケット不動産の渋谷です。
お盆や年末年始に帰省すると、親御さんの体調や暮らしぶりが気になり、「この家、どうする?」という話題になりがちです。今回は認知症の進行が疑われる方の不動産売却について、現場目線で「まず何を確認し、どう進めるか」を整理します。法的な要点も最小限で分かりやすくまとめました。
まず結論(超要約)
-
ご本人の「意思能力」(契約の意味を理解できる力)が疑わしい状態での売買契約は、無効と争われるリスクが高い。
-
その場合は、**家庭裁判所の手続(後見制度)**を使って、適法・安全に進めるのが基本。
-
居住用不動産の売却には、後見人が選任されても家庭裁判所の許可が必要。
-
すでに任意後見契約が登記済みなら、原則その枠組みが優先。例外的に本人の利益のため特に必要なときだけ、法定後見の開始申立てが可能。
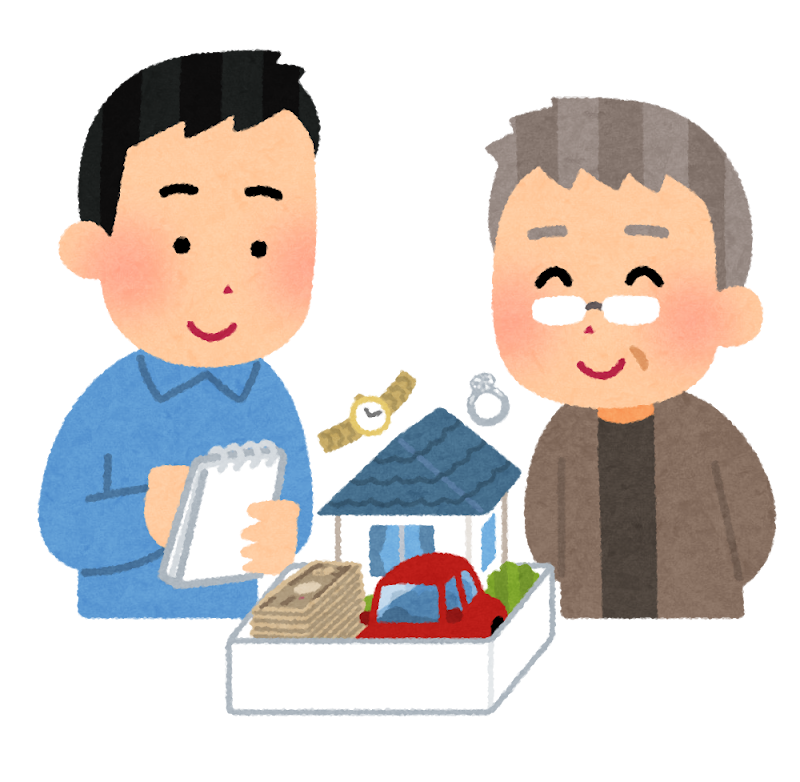
キホンの用語だけおさえる
-
意思能力:自分の契約行為の法律効果を理解できる力。これが欠けていると契約は無効リスク。
-
法定後見(成年後見・保佐・補助):判断能力が低下した後に家庭裁判所が支援者(後見人など)を選ぶ制度。
-
任意後見:判断能力が十分なうちに、将来の財産管理を誰に任せるかを本人の意思で契約(公正証書)しておく制度。家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で効力がスタート。
よくあるご質問(リアル事例を短く)
Q1. 母がAさんと任意後見契約を結び登記も済。Aさんが不適任だと感じる。別の人を成年後見人にできる?
A. 原則はできません(任意後見が先に立つため)。ただし、本人の利益のため特に必要なときは、成年後見開始の審判を求めることができます。
→ 実務的には、「Aさんが不適任である具体的事情」「本人利益の具体的侵害・危険」を客観資料で示す準備が鍵。
Q2. 90歳の父が施設入居中。「誰も住まない家を売りたい」と言い出した。ただ、簡単な計算もおぼつかないことがある。売れる?
A. そのまま契約すると無効リスクが高い。
家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、選任後に居住用不動産売却の許可申立てをして進めるのが安全。
※ 施設入居中でも、将来住む可能性が残る自宅は「居住用不動産」扱いとなり得るため、裁判所の許可が必要。
実務フロー(現場で失敗しない段取り)
-
現状把握
-
かかりつけ医で診断書(認知機能に関する所見)を取得。
-
後見登記等の登記事項証明書を取り寄せ、任意後見契約の有無・範囲を確認。
-
-
スキームの判断
-
任意後見が登記済み:
-
任意後見監督人の有無・権限を確認。
-
不適任が疑われる場合は、**「本人利益のため特に必要」**を基準に、法定後見開始の申立ての可否を検討。
-
-
任意後見がない/機能していない:
-
成年後見(法定後見)の申立てを検討。
-
-
-
家庭裁判所の手続
-
後見人候補者(ご家族や専門職)を決め、申立書類を整える。
-
選任後、居住用不動産売却の許可申立てを別途行う。
-
-
売却の準備(許可前にやり過ぎない)
-
価格査定・売却戦略の素案は作るが、契約・引渡しの確約はNG。
-
許可がおりてから、条件交渉→売買契約→決済・引渡しへ。
-
-
決済・引渡し
-
後見人が代理人として契約締結。
-
資金の受領・使途は本人利益に合致するよう、帳簿・領収書等を厳格管理(後見人の報告義務)。
-
必要書類の例(状況により変わります)
-
医師の診断書(認知機能に触れたもの)
-
後見登記等の登記事項証明書
-
戸籍・住民票・固定資産税関係書類
-
不動産の権利証(登記識別情報)・評価証明
-
任意後見契約公正証書(該当時)
-
後見開始申立書一式/居住用不動産売却許可申立書一式
スケジュール感の目安
-
後見人選任まで:数週間~数か月
-
売却許可の取得まで:追加で数週間程度
-
市場状況により、販売~成約も含めると全体で数か月スパンを想定しておくと安全です。
よくある落とし穴(回避策つき)
-
許可前に買主と合意・手付受領 → 許可が出ずにトラブル。
-
回避: 許可取得後に本契約。どうしても先に動くなら停止条件の設計を。
-
-
親族間の温度差 → 後から異議・取消主張に発展。
-
回避: 重要局面では同席説明・議事録化。
-
-
価格が相場とかけ離れる → 後見監督・裁判所から本人不利益と判断される恐れ。
-
回避: 複数査定と根拠資料(成約事例・評価書)を整備。
-
そのまま使える連絡テンプレ
仲介会社への初回相談メール(例)
件名:親の自宅売却について(後見手続き前提の相談)
本文:
親の認知機能低下が疑われ、後見手続を前提に売却可能性を検討しています。
①想定売却価格レンジの査定、②許可取得までのスケジュール感、③許可後の販売戦略の素案
の3点について、守秘のうえ助言をお願いします。必要資料のリストもご教示ください。
まとめ(社長的・実務三箇条)
-
まず法的枠組みを確認:任意後見の登記有無→後見手続の要否へ。
-
医師の所見と客観資料で固める:無効リスクを「予防」する準備。
-
家庭裁判所の許可がゴールゲート:許可前は“準備”に徹する。
ロケット不動産のサポート範囲
-
価格査定・売却戦略の設計(許可取得を前提としたドラフト)
-
後見・許可を想定した契約条項の提案(停止条件・日程設計等)
-
専門職(弁護士・司法書士等)との連携による安全運行
※本記事は一般的な実務の流れを解説したもので、**個別事案の法的助言ではありません。**具体の案件は、必ず専門家へご相談ください。
帰省で「そろそろ考えないと…」となったら、まずは現状整理から。
資料の集め方・初回査定の出し方まで、静かに、ていねいに伴走します。お気軽にご相談ください。